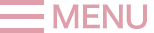相続人が子供(未成年・胎児)のときの相続と遺産分割協議
いつの時代でも深刻な問題となりやすい相続問題。なかでも厄介になりやすいのが、相続人が子どもであった場合のケースです。
相続人が未成年者もしくは胎児で会ったりする場合、どのように相続が行なわれるのか、そもそも相続権があるのか、など親族としては気になるところではないでしょうか。
そこで、今回は相続人が子どもであった場合の相続や分割協議などについて詳しく解説していきます。
目次
相続人が未成年である場合
相続人が未成年の子どもである場合、本人が遺産分割協議に参加することとなるのかは気になる部分です。
まずは、相続人が未成年であった場合について、詳しく見ていきましょう。
親権者が相続人でないケース
相続人が未成年であり、なおかつ親権者が相続人でない場合、基本的に親権者が法廷代理人として遺産分割協議を行います。子どもの年齢によっては、本人が協議に参加して有利に動くことは現実的ではありません。
親権者として認められている父母であれば、仮に親が相続人でなくても未成年の子どもに代わって遺産分割協議に参加することが可能です。
本ケースが該当する例としては、子どもの両親が離婚して母親に引き取られた後、父が亡くなったときには母親は相続人ではありませんが、子どもは相続人に該当します。この場合は、母親が代理として遺産分割協議に参加可能です。
親権者が相続人であるケース
親権者が相続人である場合には、親権者自身の相続問題と子どもの相続問題の2つを同時に抱えることとなります。たとえば、両親が結婚中に父親が亡くなったとき、母親は自分と子どもの立場から遺産分割協議に参加するのかは疑問でしょう。
しかし、親も子も相続人である場合は、親が子どもの代理として遺産分割協議に参加することはできません。そもそも遺産分割協議は、相続人同士で話し合って遺産をどう引き継ぐかを決定する場です。相続人同士で対立することが考えられることから、仮に親が子どもの代理で協議ができてしまうと、子どもにとって不利な取り決めがなされてしまうリスクがあるのです。
上記の場合は、母親はあくまでも自分の立場からのみ遺産分割協に参加することが可能であり、子どもは特別代理人の専任を請求して遺産分割協議を行なわなければなりません。
ちなみに、特定代理人は相続そのものに利害関係のない人間であれば、誰を選出することも可能です。ただし、特定代理人は必ず専任しなければならず、万が一特定代理人が不参加で協議を行っても決定事項は無効となります。
相続人が胎児の場合
妻が妊娠中に父親が亡くなるなど、相続人が胎児である場合には、どのように相続を進めていくのか気になる部分です。
ここからは、相続人が胎児である場合の相続について解説します。
胎児でも相続人に該当する
相続人が胎児であっても、民法に基づき相続人として該当します。本来、民法では人としての権利は出生に始まるとされています。しかし、出生しないと権利がないといったルールでは、すでに生まれている子どもと胎児とで、相続における不公平が生じてしまいます。これを回避するために、例外として胎児の相続が認められているのです。
つまり、仮に生まれていない段階であっても、相続人としての立場があります。
ただし、万が一胎児が死産などで生まれなかった場合には相続の権利はなくなります。遺産分割協議が成立した後に死産になった場合には、協議をやり直す必要があることを覚えておきましょう。
遺産分割協議では「代理人」を選定する
胎児の遺産分割協議では、「代理人」を選定します。前項のケースと同様、母親が相続人である場合には胎児の代理人を努めることはできません。相続において利害関係のない第三者が代理人を務めることが重要です。
なお、胎児の段階では無事に出生するか否かが分からないといった懸念もあります。よほど急いで協議をしなければならないケースは除き、なるべくは胎児の出生を待ったうえで遺産分割協議を行うことがおすすめです。
相続人問題は弁護士への相談も重要
相続人における遺産分割協議や相続の問題は、弁護士などのプロに依頼することも重要です。相続における法律は複雑で分かりにくい部分も多いものです。相続人の間での知識差によっては、自分や子どもが不利な状況で成立してしまう可能性も否めません。
弁護士事務所によっては、初回無料相談を設けているところも多いため、なるべく無理のない範囲で相続を進めていくためにも、弁護士に相談してみましょう。
参考:大阪で遺産相続トラブルに強い弁護士無料相談 – 梅田パートナーズ法律事務所
おわりに
本ページでは、未成年者や胎児の相続問題について解説しました。基本的にはいずれの場合であっても相続は可能です。しかし、親が相続人であるか否かや、胎児が無事に出生するかで状況は大きく変化します。
まずは、本ページを参考にしながら、自分と子どものケースを理解し、どのような対応が必要となるのかを考えてみましょう。”